
世界的な観光都市である京都。その中心部にキャンパスを構える京都府立大学は、文学部、公共政策学部(2026年度より社会科学部に改称)、農学食科学部、生命理工情報学部、環境科学部の5つの学部を擁する公立大学です。
少人数教育を大切にしており、学生と教員の距離が近いのが大きな特徴で、授業や研究での相談がしやすい環境が整っています。
さらに、このような風通しの良さが、独自の「留学制度」を生み出しています。
京都府立大学の留学制度は、短期研修から半年単位の交換留学まで幅広く、学生一人ひとりの希望に合わせた選択が可能です。
なかには学生の声がきっかけで新たに協定が結ばれたプログラムもあり、非常に柔軟で実践的な取り組みが進んでいます。
今回は、京都府立大学の山口美知代 副学長兼国際センター長に、同大学の留学制度や国際化の現状について、くわしくお話を伺いました。
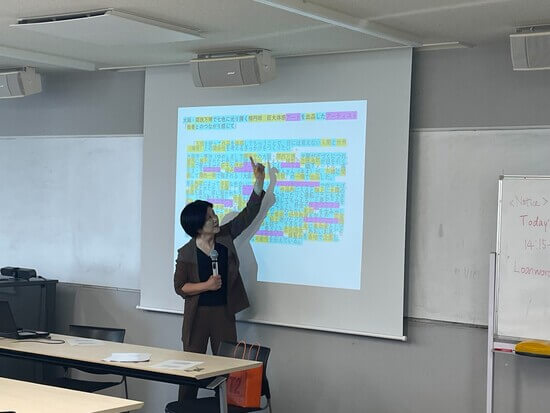
目次
京都府立大学は「自文化」を大切にしながら国際教育に力を入れる
── まずはじめに、京都府立大学のグローバル教育への考え方について教えてください。
今は多文化共生の時代と言われていますが、本学でもその実現のためには、多様性を認めることが大切だと考えています。そのために欠かせないのが、やはり外国語でのコミュニケーションです。
最近では生成AIや機械翻訳を使えば、外国語でのやり取りは以前よりずっと簡単になってきました。ただ、それでも肉声での対話や、人と人とが直接言葉を交わすことの大切さは変わりません。
本学ではそうした点を大切にしながら、グローバル教育を推進してきました。もちろん、自国の文化について理解を深めることも同時に重要だと考えています。
── ありがとうございます。近年は、キャンパスの国際化も進んでいるとお聞きしました。
じつは、京都府立大学がここまで国際化してきたのは、ここ数年でのことです。
というのも、以前から中国との緊密な協定関係があったりと、積極的に国際交流が行われてきました。ただ、その頃は留学生の出身国が限られている部分もありました。
近年は状況が大きく変わり、キャンパスにいるだけで多様な国籍の学生と交流できるようになってきています。
これは、2020年に塚本康浩学長が就任して以来、進められてきた国際化の取り組みの成果が現れ始めているのではないかと感じています。
学生の声から生まれたラトビア・リガ工科大学との協定関係

── 京都府立大学の留学制度には、どのような魅力があるのでしょうか?
京都府立大学はさまざまな国と協定校の関係を持っていますが、その中でも、ラトビアにあるリガ工科大学は特に人気があります。
じつは、この大学との交流は、最初は本学の学生が私費で留学をして「とても良かった」と帰国後に報告してくれたことがきっかけでした。
その後、京都府立大学の教員が現地を訪れて正式に協定を結ぶことになったのです。
── 学生の声がきっかけになるとは、驚きました。本当に風通しのよい大学なのですね。
そうですね。小規模ながらも、学生の声に耳を傾けながら新しいつながりが生まれていく。本学にしかできない“手作り感”あふれる留学制度の一例だと思います。
実際に私もラトビアを訪問しましたが、人々がとても親切で安全な国だと感じました。
旧ソ連に属していた歴史を持ちながら、同時にドイツ文化の影響も色濃く残す国で、現在では中世の面影を残す素晴らしい石畳の街並みが広がっています。
もちろん、現地の言葉であるラトビア語があるわけですが、授業は英語で行われており、日常生活でも英語が通じる環境です。そのため、学生からも人気が高い留学先となっています。
また、2025年の日本国際博覧会(大阪・関西万博)では、ラトビアとリトアニアが共同で「バルトパビリオン」を出展するなど、日本でも存在感を示しつつある国の一つです。
交換留学先は欧州各国を中心に拡大中。留学制度の充実を図る

── それでは、具体的な留学先やプログラムについて教えてください。
京都府立大学では、大きく分けて2種類の留学制度があります。
1つは短期間の語学研修です。行き先としては、中国や韓国のほか、英語圏ではオーストラリア、イギリス、アメリカ、アイルランドなどで実施しています。
そして、 もう1つは交換留学です。半年単位の派遣となり、授業料が免除される制度になっています。現地の大学で専門科目を受講することができ、派遣先は先ほどお伝えしたラトビア、台湾、韓国、ドイツ、イタリア、ブラジル、そしてイギリスなどがあります。
また、全学部の学生向けに、本学で定めた協定校への短期語学留学をした場合、それを教養の単位として認めています。(講義名:海外語学研修Ⅰ・海外語学研修Ⅱ)
さらに、学部・学科によって留学先の取得単位の扱いを定めており、たとえば文学部ではドイツ・レーゲンスブルク大学への5か月留学での取得単位を専門単位として認めています。
とくに近年では、欧州各国の大学との協定を推進していて、英語での履修が可能な大学への交換留学先の開拓に努めています。様々な地域の大学と協定を結び、留学を希望する学生のニーズに応えるべく活動中です。
少人数だからこそ留学や海外研修に行けるチャンスが豊富

── 留学プログラムには毎年どのぐらいの学生さんが参加されていますか?
国際センターが実施している留学プログラムへの参加数は年間約40名ほどです。
加えて、学部ごとに専門分野に特化した留学制度もあります。そういった研究室単位での海外研修なども含めると、60名程度になるかと思います。
── 交換留学を希望する場合、どのような選考方法で参加者が決まるのでしょうか?
選考は、学生と教職員との面談を通じて決定します。現在のところ、参加希望者が定員を上回ることはほとんどないため、学生の皆さんには満足のいくサービスを提供できていると考えています。
参加希望者と受け入れ可能な席数とのバランスが取れており、仮に特定の留学先に希望が集中した場合でも、国際センターのスタッフが「こちらのプログラムはどうですか?」といった形で相談しながら、最適な留学先を提案しています。
──「専門分野に特化した留学制度もある」とのことですが、具体的な内容を教えてください。
たとえば、環境科学部森林科学科の学生を対象に実施された、インドネシアの短期研修プログラムです。
日本とインドネシアの学生それぞれ10数名が、2週間ずつ相互に訪問し合います。現地では、インドネシアの熱帯林の保全や管理について学び、日本では京都府の林業や府立大学の演習林を視察してもらうなど、専門性の高い実地研修を行っています。
同プログラムは、京都大学および三重大学との合同プロジェクトとして実施されており、インドネシアのムラワルマン大学と毎年継続的に交流を行っています。
近年では、費用面や就職活動との両立を考慮し、「短期での海外経験」を希望する学生が増えていることから、今後もこのような短期プログラムの充実に力を入れていきたいと考えています。
京都府立大学の留学に関する奨学金制度や相談窓口について
── 留学を希望している場合、奨学金制度などの支援は利用できますか?
京都府立大学では、毎年度JASSOの海外留学支援制度の認定を受けている他、寄付金によって設立された「池田栄一学術振興基金」というものがあります。
また、本学は公立大学法人の傘下にあるため、公立大学法人からの奨学金制度も利用できます。
── 他に、学内での留学相談のサポートにはどのようなものがあるか教えてください
まずは、京都府立大学「国際センター」が各種相談を受け付けています。
国際センターでは、留学を希望する学生の準備を補助するため、海外留学に係る保険の紹介、手続きのアドバイスまで行っています。
また、本学は教員と学生の距離が近いことが大きな特徴です。そのため、授業担当やゼミ担当の教員に直接相談される学生も少なくありません。
さらに、昼休みには「国際センター談話会」が開かれています。この会では、外部講師や留学経験者を招いて、学生向けの懇談会やミニセミナーなどが行われます。
このほか、先日は本学でTOEFLの試験を実施しました。通常は数万円かかる受験料を特別価格で提供してもらうなど、学生さんの経済的な負担を減らす取り組みも行っています。
学生の力で国際交流や留学を盛り上げる「KPU SIPS」の活動
── 次に、大学のキャンパス内での国際交流について教えてください。
京都府立大学では、有志の学生による SIPS(Staff & Student Initiative for Promoting Study Abroad)という団体が活動しています。
SIPSとは、文部科学省傘下の「トビタテ!留学JAPAN」事務局を母体とし、全国60以上の大学で留学促進のための職員や学生が中心となり組織されたものです。
京都府立大学でも「KPU SIPS」として2024年7月に発足し、現在は23名のメンバーが参加しています。国際的な学びの機会を広げ、異文化理解を深めることを目標に活動を続けています。
このほか、夏休みに協定校の学生を約20名ほど京都へ招き、「国際京都学夏季セミナー」(Kyoto KPU Summer Seminar, KKSS)という1週間のプログラムを実施しています。
── 素晴らしい取り組みですね。京都だからこそ生まれる国際交流の形だと感じます。
そうですね。セミナー期間中は、京都の歴史や自然についての英語講義が行われます。また、文化アクティビティでは茶道部、書道部の協力を得て京都ならではの体験を選べるほか、学外に出かけてのフィールドワークも企画されています。
今年で3回目を迎えましたが、今回は留学生にも人気の日本のアニメや外来語などの題材に焦点を当てました。学生主体の温かいサポートのもと、全日程を無事に終えることができました。
このように、京都にいながらにして、ドイツやイギリスや台湾の学生たちと交流する、そういう機会も設けたりしています。
京都府立大学が取り組む留学制度の今後について
── 今後、留学制度に関してとくに力を入れたい取り組みはありますか?
京都府立大学では、海外協定校への交換留学を希望する学生の数は年々増えています。ですが、実際に派遣される学生はまだ限られており、実績のない大学も多いのが現状です。
そこで国際センターでは、留学から帰国した学生から現地の詳しい状況や留学先の雰囲気を聞き取り、情報の蓄積に力を入れています。
たとえばイギリスの交換留学枠が新たに設けられても、語学力や準備不足で手を挙げられない学生も多いです。
より多くの学生に挑戦してもらうためには、入学時から利用できる留学のチャンスについて早い段階で知ってもらい、必要な準備をしっかり進められるようにしたいと考えています。
そして、2年生や3年生になったとき、安心して留学にチャレンジできるようなサポート体制を整えていきたいと考えます。
留学制度についてはオープンキャンパスやパンフレットで情報収集
── 留学制度についてくわしく知りたい受験生は、どこで情報を得ることができますか?
京都府立大学のホームページや大学案内の他、オープンキャンパスなどで留学に関する情報を発信しています。
とくにオープンキャンパスでは、各学部ごとの詳細な説明を聞いたり、学部の特色やカリキュラムについて直接質問することも可能です。
さらに、国際センターでは「留学相談コーナー」を設けており、実際に訪れて相談することで、留学制度や手続きの流れ、サポート体制などについて具体的な情報を得ることができます。
── 実際にキャンパスを訪れることが難しい場合はどうすればいいですか?
国際センターではメールでのお問い合わせにも対応していますので、お気軽にご連絡ください。
加えて、デジタルパンフレットの「キャンパスガイド(大学案内)」や「ふたはの桂」では、各学部情報や就職活動に関する先輩インタビューなども掲載されています。
留学のことだけではなく、大学生活や進路を考える時の参考としても役立つ内容です。これらの情報はホームページでも公開されていますので、ぜひご覧ください。
京都府立大学の山口副学長から高校生や受験生へメッセージ
── 京都府立大学の受験を検討している高校生へ向けて、メッセージをおねがいします。
京都は、世界中から多くの外国人が訪れ、国際色豊かな都市です。
その一方で、歴史的な建造物も非常に多く、日常的に歴史や文化が根付いている街です。現代的なものと歴史的なものを同時に感じられる、珍しい場所だと思います。
私たち京都府立大学は、学生ひとりひとりの声に耳を傾け、それぞれの学びを大事にする大学です。
受験を考えている方は、メール1本でも、オープンキャンパスでも、少しでも関わりを持っていただければ、そこから色々なつながりや魅力を感じていただけると思います。
私たち京都府立大学は、これからも国際化をさらに進めていきます。
長い歴史を持ち、また世界中から観光客の訪れる京都で学ぶことは、多文化理解と伝統の尊重の両方に道を開く営みです。
ぜひ、京都府立大学でお待ちしております。
京都府立大学の基本情報
| 大学名 | 京都府立大学 |
|---|---|
| 学部 | 【学部】 ・文学部 ・社会科学部(2026年度~)※2025年度までは公共政策学部 ・農学食科学部 ・生命理工情報学部 ・環境科学部 【大学院】 ・文学研究科 ・社会科学研究科(2026年度~)※2025年度までは公共政策学研究科 ・生命環境科学研究科 |
| 所在地(住所) | 【下鴨キャンパス】 〒606-8522京都市左京区下鴨半木町1-5 【精華キャンパス】 〒619-0244京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字大路74番地 |
| 留学プログラム | 交換留学(韓国、ラトビア、台湾、イタリア、イギリス、ブラジルなど) ※ その他、ドイツへの5ヶ月中期留学(文学部・文学研究科)のほか、英国・米国・オーストラリア・アイルランド・ドイツ・中国・韓国への短期研修プログラムあり |
| 大学公式HP | https://www.kpu.ac.jp/ |
| SNS | ・京都府立大学の公式YouTubeチャンネル ・京都府立大学の公式LINE |
※ 取材時の情報を掲載しています。
今後も留学制度の拡充が期待される!京都府立大学の取材後記
今回の取材で最も印象に残ったのは、京都府立大学がヨーロッパを中心に展開している協定留学プログラムでした。
とくにラトビア・リガ工科大学の交換留学は、学生の声をきっかけに協定が生まれたというエピソードが印象的で、教員と学生の距離の近さが、新しいプログラムの柔軟な実現につながっていることがわかりました。
学生の声をこれほど取り入れた留学制度は、なかなか見られないように思います。
また、京都府立大学では留学に限らず、大学全体として学生の意見を大切にする雰囲気が根付いています。取材を通じて、こうした教育方針がしっかりと伝わってきました。
また、それ以外にも、英語圏であるアメリカ・イギリス・オーストラリアの他、韓国・台湾などの短期研修プログラムも準備されています。
少人数制の大学ならではの手厚いサポートのもと、教員と学生の距離が非常に近く、留学に関する相談や準備も気軽に行える点は、他大学には見られない強みでしょう。
京都府立大学の留学制度は今後ますます充実し、全学部の学生が世界とつながるチャンスが広がっています。興味のある方は、ぜひオープンキャンパスやホームページで最新の情報をチェックしてみてください。
取材日:2025年9月3日
取材/文:永谷 知香
写真提供:京都府立大学 国際センター





