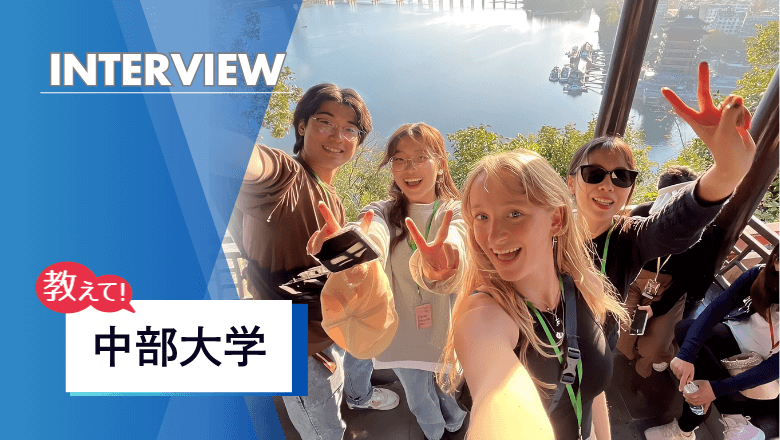宮城大学は、宮城県に大和キャンパス(黒川郡大和町)と太白キャンパス(仙台市)を構える公立大学です。
看護学群、事業構想学群、食産業学群といった多彩な学びのフィールドの学群を備え、学生一人ひとりの興味や将来像に合わせて専門性を深められます。
なかでも注目したいのは、教員自らが企画・運営する独自の留学制度です。学生の成長に本当に必要な学びを考え抜いたプログラムだからこそ、安心して海外に挑戦できる環境が整っています。
「学生一人ひとりが個性を持った、“出る杭”に。」
その想いを形にするため、短期研修から長期留学まで、世界に飛び出すチャンスが用意されています。
今回は、宮城大学の国際交流・留学生センター長の曾根教授、留学カウンセラーの三浦さん、事務局の企画・入試課の松村さんの3名に、同学の留学制度についてお話を伺いました。
目次
宮城大学は「プッシュ・プル・グロー」で国際教育を進める

── はじめに、宮城大学の国際教育の考え方について教えてください。
宮城大学では、国際教育において「プッシュ(PUSH)」「プル(PULL)」「グロー(GROW)」という3つの領域に力を入れています。
「プッシュ(PUSH)」はその名の通り、学生を海外へ送り出す取り組みです。海外への派遣は主に「短期」と「長期」の2段階がありますが、実際に、短期研修に参加した学生の7〜8割は、「次は長期で行きたい」と希望して戻ってきます。
まずは短期で海外に触れ、その体験をきっかけに長期留学へとステップアップしていく。こうした流れを意識しながら、指導体制も段階的に整えています。
次に「プル(PULL)」は、海外からの学生の受け入れです。協定校からの留学生の受け入れにも力を入れています。そして最後の「グロー(GROW)」は、学内で国際的な視点を身につけてもらう取り組みです。
キャンパス内で行う国際交流イベントや、国際的な授業などを通じて、国内にいながらも多文化と触れ合える環境をつくっています。
── 海外に行けない学生に対しても、国際的な視点を育む工夫をされているんですね。
海外留学をするには、経済的・時間的な制約もありますので、学生全員が参加できるわけではありません。しかも、国際的な感覚を身につけるためには、必ずしも海外に行くことが唯一の方法というわけではないのです。
日常の中で視野を広げ、多様な価値観に触れることも非常に重要です。だからこそ、学内であってもグローバルな視点を育むための取り組みを、充実させています。
すべての学生が、どこかの段階で国際的な経験や感覚を身につけられる。宮城大学では、そのような環境作りを大切にしています。
国際看護やSDGsなど、専門性の高い海外研修が魅力

── それでは、宮城大学の留学制度の特徴について教えてください。
宮城大学の海外研修は、一般的な語学研修とは違い、少しユニークなアプローチを取っています。
英語を独立した目的として学ぶのではなく、専門分野の学びを深めるための手段として活用しているんですね。たとえば国際看護の研修においては、単なる語学習得ではなく、「看護を学ぶためのスキル」として英語を使っています。
そうすることで、単なる語学研修にとどまらず、明確なテーマを設定し、実際の社会課題に取り組む学びを大切にしています。
また、もう一つの特徴として、研修プログラムを旅行会社に委託している大学もある中で、宮城大学では教員が企画から現地での指導までを担います。
宮城大学では研修地において、協定校が提供する教育プログラムに加え、宮城大学独自のグローバル指導も並行して行います。
── 海外研修プログラムを教員の方が作っているということですか?
そうなんです。国際交流・留学生センターの教員が中心となって企画し、各学群の先生方が関わることで、学群の枠を超えてアイデアを吸い上げます。
そのため、より学問的で実践的な内容になっているのが、同学の海外研修プログラムの魅力です。
例えば、SDGsをテーマにした研修では、学生が自分自身で調査したいテーマを設定するなど、より主体的な学びになるようにしています。
このような体験は、旅行会社の企画では味わえないもので、学生にとって貴重な学びとなっています。
世界を舞台に!宮城大学の5つの留学プログラム
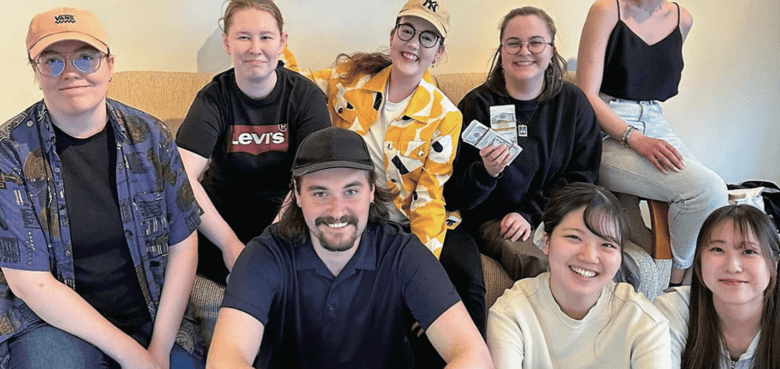
── 具体的には、どのような留学プログラムが用意されているのでしょうか。
宮城大学では短期と長期をあわせて5つのプログラムがあります。
短期には「海外フィールドワーク研修」「リアル・アジア」「ヨーロッパ研修」「実践看護英語演習」があり、長期には「アンバサダープログラム」があります。
── まず、「海外フィールドワーク研修」について教えてください。
じつはフィールドワークは、国内研修もいくつかあり、企業や公共機関を訪問して社会のリアルを体験する機会を設けています。
海外版ではこれを拡大し、実際に海外で活動しながら自分の未来像を描くことを目指しています。具体的にはアメリカ・デラウェア州のデラウェア大学で約1ヶ月間、英語研修とともに実施されます。
始めの一週間は教員が引率するので、初めての海外生活に不安がある学生でも安心して参加することが可能です。
── 次に、「リアル・アジア」と「ヨーロッパ研修」についてはいかがでしょうか。
「リアル・アジア」は、アジア圏との交流を重視する宮城県の方針に沿って始まった、本学の中でも歴史あるプログラムです。
以前はベトナムに特任教授を置き、現地のコーディネートをしてもらうなど、単なる海外研修ではできないような、とても内容の濃い研修を行っていました。
近年では、マレーシアや、広域のアジアとしてオーストラリア、今年度はグアムでも研修を実施予定です。研修では、SDGsに取り組むNPO、難民の教育施設の訪問や文化施設見学などを通じて実践的なコミュニケーション能力とグローバルな視点を養っています。
また、「ヨーロッパ研修」については、“戦争と平和”というテーマでオランダを訪問しました。学生が事前に授業で学んだ内容を踏まえ、実際の場所を訪問しながら、教授のネットワークを活用して専門的な施設を見学したり、研究者から直接講義を受けたりすることができました。
今後もテーマに応じて、さらに国の範囲を広める予定です。
──「実践看護英語演習」についても教えてください。
「実践看護英語演習」は、本学の看護学群の学生のみを対象とした、1週間ほどの短期研修です。
2023年度はシドニー看護研修、2024年度はニュージーランド看護研修を実施しました。
研修では、英語を用いて現地の医療現場を理解し、実践的な知識や国際的な視野を養うことを目的としています。実際に海外の病院や福祉施設などを視察し、各国の保健医療や看護の現状、さらにはその文化的・歴史的背景を学ぶ貴重な機会となっています。
そして、これらの短期研修プログラムには、単位として認定されるものと、そうでないものがあります。単位が付与される研修は、よりアカデミックな内容で構成されており、学内での厳格な審査を経てプログラムが設計されています。
学生からは、単位の有無にかかわらず、いずれの短期研修も非常に高い評価を得ています。
──最後に、長期留学の「アンバサダープログラム」の内容を教えてください。
アンバサダープログラムは長期派遣プログラムで、本学の協定校に約1年間派遣されます。
現在はフィンランドのトゥルク応用科学大学(TUAS)が主な送り先で、学生は専攻の学習の延長だけでなく、その国の文化や多様な価値観を直接体感しています。
滞在中には近隣諸国を訪れる学生も多く、ヨーロッパならではの多様な文化や価値観に触れることで、国際感覚をさらに深める絶好の機会となっています。
協定校の派遣先については、フィンランド以外に、オーストラリアやイタリアなどへ広がっており、今後は費用負担の軽減などの課題も解決しながら、さらに多くの学生に機会を提供したいと考えています。
宮城大学の留学プログラムの派遣数や選考基準について
── 宮城大学の留学プログラムには、どれくらいの学生の方が参加されていますか?
昨年度(2024年度)の国際プログラムへの参加者は、短期・長期あわせて23名です。
まず長期の派遣プログラムについては、本学の協定校、フィンランドのトゥルク応用科学大学の1年間のプログラムへ2名の学生を送り出しました。
そして、短期のプログラムでは、全部で21名が参加しています。
内訳については、「海外フィールドワーク研修」は、アメリカ・デラウェア大学の約1ヶ月間のプログラムに6名の学生が参加しました。
それから「リアル・アジア」は、昨年はオーストラリアで実施していて、8名。「ヨーロッパ研修」はオランダのプログラムに、5名が参加しています。「実践看護英語演習」は、ニュージーランドでの看護研修に看護学群の学生2名が参加しました。
── ありがとうございます。では、留学に参加するための選考基準などを教えてください。
選考基準については、プログラムや行き先によって多少異なります。基本的にはGPA(成績)や語学力を参考に、面談を通して学生の意欲や目的を確認するようにしています。
宮城大学の短期プログラムに関しては、教員自身が企画してることも多いです。その教員が直接学生と話をして、プログラムの趣旨に合っているかどうかも含めて、総合的に判断しているという形ですね。
宮城大学の奨学金制度「トビタテ!MYU留学サポート」が留学を後押し

── 宮城大学では、留学に関する奨学金制度などはありますか?
まずは、大学独自の「トビタテ!MYU留学サポート」という奨学金制度を用意しています。
※ MYU=宮城大学(Miyagi University)の略称
この制度は、学生自身が企画した海外での活動を応援するもので、個性豊かで多様な学生や、大学内外で活躍するリーダーの育成を目指しています。そうした活動がほかの学生にも良い影響を与え、大学全体にいい波及効果をもたらすことも期待しています。
その年の応募者数や活動内容によって、1人あたりの支給額は変動しますが、独創的な留学計画を実行したい学生に支援が届くようにしています。
宮城大学独自の奨学金制度ですので、返済不要のため卒業後の負担もありません。
もう一つは、全国的に知られている「JASSO(日本学生支援機構)」の奨学金も活用しています。これは協定校への派遣が条件になっていて、短期・長期を問わず、対象となる学生に支給されます。
── 留学を考える学生は、ぜひとも視野に入れたいですね。
宮城大学では、奨学金を通じてより多くの学生が安心して海外に挑戦できるよう、制度面からもしっかりと支援していきたいと考えています。
なお、「トビタテ!MYU留学サポート」奨学金を利用して長期留学している学生には、毎月動画での報告をお願いしています。
学生が自分で撮影した動画には、留学先のキャンパスの紹介や研究テーマについて語る場面、さらにインターンシップの体験談などが含まれています。そのため、内容がとてもリアルに伝わってきます。
このように、在校生に自分と同じ宮城大生が海外で奮闘している姿を見てもらい、「自分も行ってみたい」と感じてもらえるような仕組みができています。
留学準備で頼りになる、先輩の声や「コモンズ」の存在

── 留学が決まった学生への、サポートなどがあれば教えてください。
留学カウンセラーによる個別相談を随時受け付けており、留学が決定してからも準備から帰国までサポートしています。
留学準備には様々な手続きが必要ですが、「どこから手をつけたらよいのか」「ビザの発行までどの位時間がかかるのか」などの疑問については、過去に渡航した学生のデーターも参考にしながらアドバイスを行っています。
また、学内の専用サイトでは留学プログラムの内容紹介や、過去の参加学生の報告などを掲載しています。
学生が留学に期待を膨らませながら、渡航準備や現地での生活のヒントを得られるよう、実用的な情報を提供しています。
── 先輩の声は心強いですね。ちなみに、宮城大学には「コモンズ」と呼ばれるスペースがあると伺いました。
この「コモンズ」はキャンパス内にあり、学生が主体的に自主学習や研究などさまざまな活動に自由に取り組める場所です。
特に、国際交流に関心のある学生たちの拠点となっている「グローバルコモンズ」には、英語教材やスピーキング練習等に使用できる個別スペース、快適なソファーなどが用意されています。そのため、学生同士が気軽に交流できる環境となっています。
また、Student Assistant(スチューデントアシスタント)という立場の学生たちが、イベントの企画や運営もしています。
たとえば、留学から帰ってきた学生へのインタビューを企画したり、留学生に自国の文化を紹介してもらうイベントを開いたりすることも、彼らの活動です。すべて学生が主体になって進めているので、とても活発な場所となっています。
── 「グローバルコモンズ」での国際交流は、学生にどういった影響をもたらしていますか?
グローバルコモンズでは、短期受入留学生にとっても彼らの居場所として過ごしてもらっていますので、在校生とも自然に会話する雰囲気が生まれ、多文化の相互理解に役立っています。
実際に、「話してみたら英語通じた!」という自信や「現地に行って体験してみたい」という意欲がわき、長期での留学を希望するようになった学生もいます。受入学生が帰国したあと、今度は宮城大生がその受入学生の大学へ行く、という流れもできつつありとても良い相乗効果が生まれていると思います。
現地に知っている人がいるだけで、安心感がまったく違います。そのため、このようなつながりはとても大切だと思います。
私自身も、グローバルコモンズの中に常駐していて、学生たちと日常的に会話するようにしています。いきなり「留学の相談です」とは言いづらい学生も多いので、まずは気軽に話せる関係をつくることを意識してますね。
それに、留学から帰ってきた学生に対しても、急に英語環境がなくなってしまうことで少し戸惑う学生もいるので、帰国後も英語で参加できるようなイベントに声をかけたりしています。
プログラム説明会では、実際に経験者の方に話をしてもらうことで、次の学生たちにバトンを渡していく仕組みにしています。このようにして、先輩から後輩へと関係がつながっていくよう心がけています。
留学情報は公式HPで取得できる!オープンキャンパスでの相談も可能

── 宮城大学の留学に関する情報を知るには、どのような方法がありますか。
留学制度に関する情報は、国際交流・留学生センターのホームページにて随時公開しております。海外の協定校の一覧なども、そちらに最新情報を掲載しております。
また、具体的な留学プログラムの詳細は、毎年内容が変わることもありますので、入学後に学内向けの専用サイトのみで公開しています。「今年はこの国、この大学へ派遣します」といった内容が、その都度更新されます。
── オープンキャンパスなどのイベントで、留学制度について直接説明を受けることはできますか?
もちろんです。オープンキャンパスの際には、国際交流・留学生センター(CIEOS:通称シーオス)が専用のブースを設けています。
そこで私たちが直接、プログラムの内容や取り組みについてご説明しています。
興味のある高校生や保護者の方にも、実際にどういった活動を行っているのかをご紹介していますので、直接話を聞いてみたいという方には、とても良い機会です。ぜひお待ちしております。
宮城大学から留学に挑戦したい受験生や高校生へメッセージ

── 宮城大学への進学や留学を考えている高校生の皆さんに向けて、メッセージをお願いします。
曾根教授(国際交流・留学生センター):宮城大学では、他では出会えない海外体験を用意しています。
本学の留学や海外研修は、教員や職員が自ら現地を開拓し、学生の成長に本当に必要なプログラムを一からつくり上げているんです。だからこそ、ちょっと変わった、知らなかった世界に触れられる。
ここでしか味わえないような海外体験を、この宮城大学で一緒に経験してほしいと考えています。
三浦さん(同上):最近あった嬉しいエピソードなのですが、留学から帰ってきた学生が話してくれた言葉が、とても印象的でした。その学生は、留学に行く前に「このまま大学生活を終えたくない。でも、自分に何ができるのか分からない」と悩んでいました。それでも、思い切って「今しかできない経験」と考え、留学を選ぶことにしたのです。
実際に行ってみると、そこは人種も年齢もさまざまな人が集まる大学。英語を学ぶ以上に、相手がどういう人生を歩んできたのかを知ることで、自分の可能性が大きく広がったと言います。
「あなたにはこういう仕事が向いているんじゃない?」と他の人に声をかけてもらったことで、自分では気づかなかった強みを見つけることもできたそうです。
出発前は将来への不安でいっぱいだったのが、帰国後には自分にはいろんな選択肢があると実感し、将来が楽しみになったと話してくれました。
こうした気づきは、実際に海外へ出てみないと得られません。だからこそ、宮城大学では在学中にぜひ留学に挑戦してほしいと思っています。
松村さん(事務局 企画・入試課):宮城大学では学部ではなく学群と称している通り、入学したときに将来がまだ決まっていなくても大丈夫です。学びながら自分の道を考え、見つけていくことができます。
さらに、さまざまな体験を通じて新しい自分を発見できる環境も整っています。ですので、入学後にやりたいことを一緒に探しながら成長していける、そんな大学です。
迷っている人こそ、ぜひ宮城大学で可能性を広げてほしいと思います。
── 未来を担う高校生へ向けて温かいお言葉をいただきました。本日はありがとうございました。
宮城大学の基本情報
| 大学名 | 宮城大学 |
|---|---|
| 学部 | 看護学群、事業構想学群、食産業学群 |
| 所在地(住所) | 大和キャンパス(看護学群、事業構想学群) 〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑1番地1 太白キャンパス(食産業学群) 〒982-0215 宮城県仙台市太白区旗立二丁目2番1号 |
| 留学プログラム | 交換留学、短期留学、海外研修 |
| 大学公式HP | https://www.myu.ac.jp/international/ |
| SNS | ・宮城大学 公式X(Twitter)アカウント ・宮城大学 公式Instagramアカウント ・宮城大学 公式Youtubeチャンネル |
※ 取材時の情報を掲載しています。
専門分野+留学で未来を切り開く力を!宮城大学の取材後記
今回の取材では、研修内容の詳細や最新の学生派遣実績まで丁寧に教えていただき、宮城大学の留学プログラムがどのように運営されているかが非常によくわかりました。
どの研修も安定して学生が派遣されており、さすがは学内で企画・運営している、質の高いプログラムだけあるなと感じられます。
その背景には、「学生一人ひとりの成長を本気で願う」教職員の方々の想いが感じられました。
このように、宮城大学では、医療や地域創生、食品産業の専門知識を身につけながら、海外の視野を広げ、その中で語学力を一つの“ツール”として身につけることができます。
近年では医療現場でも外国人と関わる機会が増えており、この環境で学んだ学生は、社会に出て即戦力として活躍できる人材になることは間違いありません。
また、キャンパスは美しく整備され、地元の方も利用するなど地域に開かれた大学です。地域に根ざしつつも、世界を見据えた教育を推進している。それが宮城大学の大きな魅力です。
興味のある高校生や受験生の方は、宮城大学の最新の留学情報や学生の体験談をチェックしてみてください。先輩たちが「出る杭」となり、未来を切り開く様子が、次の一歩の参考になるかもしれません。
取材日:2025年9月26日
取材/文:永谷 知香
写真提供:宮城大学 国際交流・留学生センター